第二言語習得論によれば、英語学習を開始する年齢は、
Older is faster, younger is better.
との事。
これはどっちがいいということではなく、早く始めれば(発音など)よりうまくなるし、遅く始める(中学生など)場合は、短期間で学べるということ。
年齢によって学び方が違うということだろう。
今学期、改めてそのことを親子クラスで実感している。
『The Wind Brew』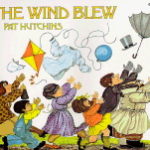
この本をリードアラウドしているのだが、本スクールでは2度目の採用だ。
4年ほど前に1回、4-5歳児を含む英語を始めて1~2年未満の、初級親子クラスで使用した。
しかし、本年度は小学1~2年生、英語も3年目以上のちょっとしたベテラン親子クラスだ。
教えるスタイルはリードアラウドだから基本は変わらないが、どこに力が入るか、内容の詳細が、図らずとも違ってくるのが興味深い。
大きな違いは、生徒の無意識的な興味(わからなくて気になるところ)が、名詞ではなく動詞に移ってくるということ。
本書の話の筋は簡単だ。
英国らしき田園で強い風が発生し、それが移動し場所を変えながらいろんなものを巻き上げて進む。そのものの、それぞれの持ち主たちが追って行く。
ここで、飛ばされるもの(名詞)の確認は、このクラスには難しいことではない。知っているものも多い。
わからないのは、どう飛ばされるかを言い表している言葉たちだ。
英語入門したてのクラスの場合、「主人公」であるthe windは、ただ「吹いて=blew away」していく、と大雑把にくくられ理解される。
しかし、本年度の「ベテラン」小学生は、それに加えて「誰のものが」、「どのように」いう情報を付け加えても、混乱がなないだろう。
これは「勘」でもあり、ちょっと「科学的」でもある。
「科学的」の根拠は、本クラス全員が、前年度末のReading Fluencyアセスメントで、英語圏G1の1学期以上の英語を読解し音読する力がある、という数字がでていること。
ということで、英語の動詞の豊かさを、そろそろ学ばせていこうと思う。
それにしても、いつも思うのだが、英語圏で「よい絵本」として長く出版され続けてきた、いわゆるロングセラーは、懐が深い。
簡単と見せて、意外と難しかったり、難しいそうでも簡単そうだったり。
何層にも読解ができる。何歳でも楽しめる部分、学べる部分がある。
そんな例が、本書の動詞の語彙。
見かけや仕立ては簡単そうな絵本だが、使われている動詞は実は難しい。
風の吹き方にもいろいろある。
みんな風の行為だが、みんな違う。
渦巻いたりwhirled,
ものを剥ぎ取ったりplucked,
うばったりsnatched,
たたきとったりwhipped,
つかみとったりgrabbed…
こういった絵本に、狭い「英語の力、〜年生程度」などの線引きはできない。
指導者も、いつも広く深い絵本の読み方を心がけたい。